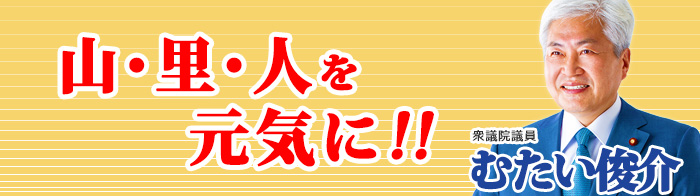理念・政策・メッセージ
2025.09.17
「宗教的境地を持つことの意味」
〜「感謝、素直、心の下座」を学ぶ〜
これまでの私の人生、その中でも政治活動を継続してきた中で、様々な宗教団体と接点を持つ機会に恵まれて来ました。神道系、仏教系、キリスト教系など様々な宗教との接点がありました。私自身も、長野県護国神社の総代会長を拝命し、実際の神社の運営に関与するなど、得難い機会を経験させて頂いてまいりました。
子供の頃、近所にある安曇野市のキリスト教団の日曜学校に通い、聖書の内容を神父様に解説して頂いたことが記憶の底流に残っています。イエス・キリストの行動、受難、福音が聖書という形で世界に広がる動きの末端に、私も接したということなのでしょう。
我々の日常生活の中でも、宗教的位置づけの行事に遭遇することは多々あります。四季のお祭り、冠婚葬祭での神事などを通じてそうした機会が存在しています。おそらく、それぞれの民族の統一性、アイデンティティーはこうした日々の行事の積み重ね、繰り返しの中から形成され、育まれてきたものなのでしょう。
こうしたものを否定する思想もありますが、それを否定する思想自体が、一つの思想、イデオロギーとして、一種の宗教性を持つことにも留意する必要があります。
ひとかどの宗教家と呼ばれる方と接すると、人格識見が高いことに感動することがあります。そうした方々のお話をじっくりと聞くと、良い話を聞けたと満足感を覚えることがあります。我々は日々の暮らしの中で、理不尽なことに遭遇したり、希望が叶えられず気持ちが落ち込んだり、不幸を託ち人生に絶望したりすることが少なからずあります。そうしたことから逃れられる人はいないでしょう。そうした場合に、宗教的境地は救いになります。
どんな不幸、災難に遭遇しても、その試練を乗り越えられる精神的状態を作り出すこと、それが宗教の究極の目的なのかもしれません。いわば、それぞれの試練に打ち勝つ「人格の完成」こそが宗教の究極的目的なのかもしれません。
最近接する機会を頂いた宗教団体の代表の方から、混乱を極める世界情勢の最中にある現在は「火の洗礼の大峠」を乗り越える途中であること、それを乗り越えるには「敬虔な祈り」が重要であり、「人間だけのご都合主義の祈り」では神の意に乗ることにはならない、と教えを頂きました。その上で、当該団体の神歌である「我良しと 想いてそぞろ 大神の 仕組みのお邪魔 致すことあり」の意味を解説して頂きました。それは、「自分自身が正しいと思ってやっていることが実は間違っていることが多々ある、良し悪しを断じることが出来るのは神だけであり、人がむやみに断じることは神の領域を犯す慢心だ」という解説でした。
ひょっとしたら、身勝手な思想でウクライナを侵略しているロシアのプーチン大統領の思い上がりや、過剰防衛によりガザを攻撃しているイスラエルのメタニエフ政権を間接的に非難しているのかとも感じたところです。この宗教家の方は、やんわりと教えを施しておられるようです。
私自身、紆余曲折がありながらも、人並みに一定の期間、人生を過ごしてきた現時点で、「感謝、素直、心の下座」という姿勢の重要性も教えて頂く機会を得て、漸くその言葉の意味を少しは理解できて来たようにも感じています。